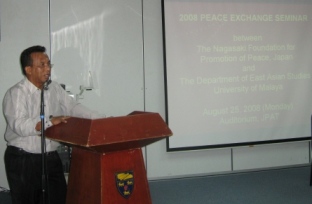ザカリアさんは合計で3度、合計13年間、日本に滞在したので
すね。大学時代からずっと日本式経営について研究され、日本企業で働いたご経験もお持ちで。
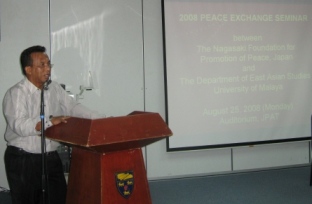
(長崎平和推進協会とマラヤ大学東アジア
研究学科との交流セミナーにて)
|
はい。日本の企業倫理の長所・短所を研究し、長所をマレーシアにいかに適用しうるかを研究しています。例えば、「5S」や、時間を守る
所、ジャスト・イン・タイム方式などです。現在は、企業帰属における企業文化というテーマで、博士論文を作成中です。吹上町で勤務していた時、鹿児島大学
の博士課程に籍を置き、日本式経営を研究していました。今年の3月までに鹿児島大学に論文を提出できるよう、現在奮闘中です。
でも今の勉強は、AAJ時代のたいへんさにはかないません。当時は漢字を覚えるのに苦労しました。でも、漢字は一文字一文字にストー
リーがあるので、勉強するのは好きでした。例えば、人が木の下にいるから「休」。人がお寺にお供えを持っていくから「持」。漢字500問テストというのが
あり、それに全問正解しました。
東京三菱銀行には、international candidate development
programという海外支店の現地人幹部を育成するプログラムがあり、2年間東京で勤務した後、海外支店に配属されます。私もこのプログラムの下で、同
期生6人とともに、東京で仕事をしていました。東京でもクアラルンプールでも、為替ディーラーとして働きました。為替ディーラーは5秒で判断しなくてはな
らない仕事で、たいへんな緊張感があり、集中力を要しました。仕事は競争の世界で、とても厳しかったです。しかし、キャリアとしてはたいへんよかったと思
います。東京にいた時に阪神淡路大震災があり、マレーシアではアジア経済危機が起こるなど、大きな事件も経験しました。
文部省奨学金で日本に留学した時は、休職して行かれたとのお話でしたが、JETプログラ
ムも休職して参加されたのでしょうか?
いいえ。銀行は辞めて参加しました。周囲の人からは、銀行を辞めてまでJETプログラムに参加するのは、自殺行為だと言われました。私
も2~3ヶ月迷いました。
他方でこの頃、自分は何のために採用されたのか?と自問することが多々ありました。日本では仕事ができるかどうかで自分のポジションや
任せられる仕事が決まりましたが、マレーシアでは日本人かマレーシア人か、日本語ができるかできないかというところでポジションや仕事が決まるという印象
を持っていました。
東方政策で日本の労働倫理を学んだマレーシア人は大勢います。その点では東方政策は成功したと思います。しかし、個々の元留学生のキャ
リア形成において、日本で学んだ経験が寄与していると必ずしも言えない部分があります。日系企業はマレーシア人をもっと信頼して、マレーシア人が経営でき
るシステムに移行していけばいいのにと思うことがありました。
とは言え、日系企業の事情も分かります。人件費と労働力の質など、様々な要素を考慮して生産拠点を決定していくわけで、ある国に拠点を
置いても人件費が上がれば別の国に拠点を移動することが往々にして起こります。その時に、管理者が日本人であれば、その人たちを別の国に動かして、そこで
生産体制を確立することができます。他方、マネージメントで現地化を進めてしまうと、そこから出て行くのが難しくなり、生産拠点を簡単に動かすことができ
なくなります。
しかし現在では、マレーシアに拠点を置く日本企業は、マネージメントを現地人に任せる体制に徐々に移行しつつあります。もう少し早い時
期からそうしていてもよかったのでは?と思うこともありますが。
JETプログラムではどのようなお仕事をされましたか?
日置市吹上町役場の地域振興係自治振興課に所属し、そこで国際交流を担当しました。特に、マレーシアの文化の紹介をすることが多かった
です。例えば、小中高校を訪問して、踊りや料理、民謡を教えるといった仕事です。吹上町には、吹上マレーシア交流実行委員会があり、現地密着型の活動が行
われていました。イベントの時には出店を出しました。またひまわり会館というところにはマレーシアコーナーが常設されていて、カレーやココナツ、マレーの
民族衣装などが売られていました。
実は、マレーシアにいた時はマレーシアの文化についてほとんど知りませんでした。国際交流員に赴任してすぐ、マレーのダンスを教えて欲
しいという依頼がありました。ダンスなんて踊ったことがなかったのですが、できないとは言えず、その依頼を受けました。インターネットで情報収集して、一
晩かけてステップをマスターし(笑)、なんとか依頼に応えることができました。今では5曲ほどレパートリーがあります。
任期中に、「里親制度」を設立しました。留学生が鹿児島に留学している間、日本人家族がその留学生の「里親」となり、何かあったら助け
るという制度です。留学生は里親を「お父さん、お母さん」と呼ぶことになっています。この制度は、留学生と日本人との関係を近づける上で、有効に機能して
いたと思います。
日置市のイベントに参加することもありました。例えば、警察が安全運転をキャンペーンする時に、マレーの民族衣装を着て、パンフレット
を配るといった活動をしました。日置市にはもう一人韓国人の国際交流員がいて、二人で様々な市のイベントに出ました。
鹿児島県には、鹿児島県マレイシア友好協会があります。フランシスコ・ザビエルが鹿児島を
訪れたのは、彼がマラッカで鹿児島の青年ヤジロウと出合ったのがきっかけだったということで、鹿児島とマラッカを結ぶ様々な活動が行われています。
 |
 |
|
(鹿児島の親善大使と一緒にマレーシアを訪問)
|

(マラッカ市長の鹿児島市訪問) |
(ザカリアさんが吹上町での国際交流員としての体験を綴ったエッセイ「恩返し」が自
治体国際化協会(CLAIR)が発行している『自
治体国際化フォーラム』に掲載されています。ぜひご覧ください。)
鹿児島での滞在は、横浜や東京での滞在とはやはり異なるものでしたか?
全然違いましたね。国際交流員の仕事は、24時間体制でした。オフィスにいるのは決まった時間だけなのですが、町民に顔が知られてお
り、どこに行っても誰かに挨拶され、おしゃべりが始まってしまいます。少しスピードを出して車を運転していたら、その後オフィスに「あんた車飛ばしとった
だろう」と電話がかかってきたこともありました(笑)。プライバシーがないので、正直疲れることもありましたが、でもそれがまたよかったのだと思います。
吹上町に滞在していた時、お米や野菜を自分で買ったことがありませんでした。誰かのお宅に寄ると、その家の人や近所の人が「これを持っ
てけ」とお米や野菜をくれたのです。家に帰ると玄関にお米や野菜が置いてあることもありました(笑)。魚もよくいただきました。
私はイスラム教徒で、鶏肉を食べることはできるのですが、イスラム教の教えに則り特定の方法で殺したものしか食べられません。日置市の
人はそれを知っていて、鳥を一羽丸ごと生きているままくれました。「これはザカリアが食べられるもの、これは食べられないもの」といろいろ配慮して選んで
くれて、私に持たせてくれました。

(鹿児島空港でのお別れ) |
後輩に一言お願いします。
日本の長所・短所とも両方学んできて欲しいです。大学の勉強だけでなく、どんどん日本社会に飛び込んで欲しいです。いろいろ制約はある
でしょうが、アルバイトをするのもよいと思います。日本人は本音と建前を持っています。日本社会に飛び込めるか否か、壁となるのは言語です。自分のことを
きちんと説明できるだけの日本語力をつけることが必要です。
宗教や文化の壁もあるけど、それはあまり重要ではなく、要は自分が飛び込むか否か、飛び込もうとする心がけがあるか否か、努力をするか
否かが問題なのです。自分が努力しない限り、壁は壊れません。マレーシア人同士で固まるのではなく、日本人や他の国から来ている留学生と交流して欲しいで
す。「失敗は成功のもと」と言います。失敗してもいいではないですか。失敗からいろいろなことを学べるのですから。
マハティール元首相は、東方政策を通じて日本人の精神や倫理を学ぶようにとおっしゃいました。それを常に頭に入れて、いろいろ学び、吸
収して欲しいです。
(インタビュー日:2009年1月23日)
ザカリア・ハジ・ムスタファさん(Mr. Zakaria Hj. Mustafa)