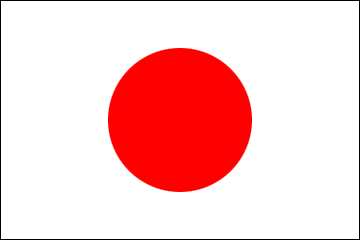2021年度(令和3年度)外務大臣表彰
令和4年2月10日
外務大臣表彰は、日本と諸外国との友好親善関係の増進に多大な貢献のあった個人および団体の功績を称えることを目的としています。
今年度、日本・マレーシア間の友好親善、交流や相互理解の増進への顕著な貢献に基づき表彰されるのは、マレーシアの個人4名と2団体です。
(個人)
1 ヴァイラッパン・マレーシア・サバ大学教授
ヴァイラッパン教授は、日本との共同研究や教育に積極的に携わってきました。同教授の主な貢献としては、地球規模課題対応国際科学技術プロジェクト(SATREPS)やサバ州での生物多様性保全に関するJICA第三国研修プログラム(TCTP)を通じた日本の研究機関との共同研究活動が挙げられます。同教授は、北海道大学及び鹿児島大学においてそれぞれ共同活動に係る大使に任命された他、東京大学と酪農学園大学において客員教授を務めてきました。 また、同教授は、マレーシアの学生と札幌啓成高校の生徒との高校生交流を開始しました。
2 クマラグル・ラマヤ・マレーシア工科大学(UTM)准教授
クマラグル准教授は、マレーシアにおける日本語教育の促進に多大な貢献をしています。 同准教授は、1998年に、マレーシア工科大学(UTM)において日本語コースを開始しました。同准教授の指導の下で、同大学はマレーシア半島南部における日本語教育の拠点になりました。 同准教授は、日本の生活や文化も熱心に教えており、この結果、多くの学生が、日本で就職したり、マレーシアの日本企業に就職したりしています。 また、同准教授の下、例年、筑波大学を含む日本の複数の大学の学生が、同工科大学に滞在し、学習や研修活動を行っています。
3 ハスパリナ・マレーシア日本国際工科院(MJIIT)日本語・日本文化センター長
ハスパリナ日本語・日本文化センター長は、2022年に40周年を迎える東方政策の下で日本語教育の促進に多大な貢献をしてきました。同センター長は、過去に、日本の国立高等専門学校(高専)に留学する学生向けコースにおいて11年間、更に、マレーシア政府が日本の円借款資金によって実施したツイニング・プログラムにて6年半、日本語講師を務めました。また、東方政策の一つの集大成として設置され、本年開校10周年を迎えるマレーシア日本国際工科院(MJIIT)での勤務は7年に及び、日本語・日本文化センター長の要職に就いています。
4 ケネス・チュン・マレーシア折り紙協会会長
ケネス・チュン会長は、2014年にマレーシア折り紙協会を設立し、様々な手段、方法を通じ、マレーシアでの折り紙の普及に熱心に取り組んでいます。同会長は、大学の講義やセミナーを通じ、コンピュータを活用し折り紙が発展していることや、医学や建築などの分野で折り紙のデザインや技法が使われていることを紹介したり、小学校や中学校での訪問授業等を通じ生徒に折り紙を教えたりしています。 また、同協会は、折り紙を用いてマレーシアの果物や植物を表現するなど、マレーシア独自の折り紙デザインの考案、作成にも取り組んでいます。
(団体)
5 教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)の日本語教員養成プログラム
教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)は、マレーシアにおける日本語教師の養成に大きく貢献してきました。 IPGKBAは、中等学校における日本語教師需要の高まりを受け、2005年に日本語教師養成プログラムを設置し、2013年までに、全国の中等学校で日本語を教える教師約70名を輩出しました。同プログラムは一度停止されたものの2019年に再開され、これまでに新たに15名が卒業し、現在8名が学んでいます。 また、2009年から現職の日本語教師に対する短期研修コースも行われています。
6 マレーシア剣道協会(MKA)
マレーシア剣道協会(MKA)は、1971年の設立以来、マレーシアにおける剣道の紹介と普及に重要な役割を果たしています。同協会の傘下には約10の道場が存在し、数百人が剣道の稽古を行っています。 同協会は、例年、各道場間の対抗戦である日本大使杯や、正しい剣道を普及させるための昇段審査、セミナーも開催しています。また、同協会は、日本文化を紹介するイベントにも参加し、剣道の基本動作や技術、道具等を説明するのみならず、日本武道の精神、心構えも教えています。 近年、同協会は、剣道の一種である居合道や杖道の稽古も行っています。
<PICTURES>
1 ヴァイラッパン・マレーシア・サバ大学教授

2 クマラグル・ラマヤ・マレーシア工科大学(UTM)准教授

3 ハスパリナ・マレーシア日本国際工科院(MJIIT)日本語・日本文化センター長

4 ケネス・チュン・マレーシア折り紙協会会長

5 教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)の日本語教員養成プログラム

6 マレーシア剣道協会(MKA)

今年度、日本・マレーシア間の友好親善、交流や相互理解の増進への顕著な貢献に基づき表彰されるのは、マレーシアの個人4名と2団体です。
(個人)
1 ヴァイラッパン・マレーシア・サバ大学教授
ヴァイラッパン教授は、日本との共同研究や教育に積極的に携わってきました。同教授の主な貢献としては、地球規模課題対応国際科学技術プロジェクト(SATREPS)やサバ州での生物多様性保全に関するJICA第三国研修プログラム(TCTP)を通じた日本の研究機関との共同研究活動が挙げられます。同教授は、北海道大学及び鹿児島大学においてそれぞれ共同活動に係る大使に任命された他、東京大学と酪農学園大学において客員教授を務めてきました。 また、同教授は、マレーシアの学生と札幌啓成高校の生徒との高校生交流を開始しました。
2 クマラグル・ラマヤ・マレーシア工科大学(UTM)准教授
クマラグル准教授は、マレーシアにおける日本語教育の促進に多大な貢献をしています。 同准教授は、1998年に、マレーシア工科大学(UTM)において日本語コースを開始しました。同准教授の指導の下で、同大学はマレーシア半島南部における日本語教育の拠点になりました。 同准教授は、日本の生活や文化も熱心に教えており、この結果、多くの学生が、日本で就職したり、マレーシアの日本企業に就職したりしています。 また、同准教授の下、例年、筑波大学を含む日本の複数の大学の学生が、同工科大学に滞在し、学習や研修活動を行っています。
3 ハスパリナ・マレーシア日本国際工科院(MJIIT)日本語・日本文化センター長
ハスパリナ日本語・日本文化センター長は、2022年に40周年を迎える東方政策の下で日本語教育の促進に多大な貢献をしてきました。同センター長は、過去に、日本の国立高等専門学校(高専)に留学する学生向けコースにおいて11年間、更に、マレーシア政府が日本の円借款資金によって実施したツイニング・プログラムにて6年半、日本語講師を務めました。また、東方政策の一つの集大成として設置され、本年開校10周年を迎えるマレーシア日本国際工科院(MJIIT)での勤務は7年に及び、日本語・日本文化センター長の要職に就いています。
4 ケネス・チュン・マレーシア折り紙協会会長
ケネス・チュン会長は、2014年にマレーシア折り紙協会を設立し、様々な手段、方法を通じ、マレーシアでの折り紙の普及に熱心に取り組んでいます。同会長は、大学の講義やセミナーを通じ、コンピュータを活用し折り紙が発展していることや、医学や建築などの分野で折り紙のデザインや技法が使われていることを紹介したり、小学校や中学校での訪問授業等を通じ生徒に折り紙を教えたりしています。 また、同協会は、折り紙を用いてマレーシアの果物や植物を表現するなど、マレーシア独自の折り紙デザインの考案、作成にも取り組んでいます。
(団体)
5 教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)の日本語教員養成プログラム
教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)は、マレーシアにおける日本語教師の養成に大きく貢献してきました。 IPGKBAは、中等学校における日本語教師需要の高まりを受け、2005年に日本語教師養成プログラムを設置し、2013年までに、全国の中等学校で日本語を教える教師約70名を輩出しました。同プログラムは一度停止されたものの2019年に再開され、これまでに新たに15名が卒業し、現在8名が学んでいます。 また、2009年から現職の日本語教師に対する短期研修コースも行われています。
6 マレーシア剣道協会(MKA)
マレーシア剣道協会(MKA)は、1971年の設立以来、マレーシアにおける剣道の紹介と普及に重要な役割を果たしています。同協会の傘下には約10の道場が存在し、数百人が剣道の稽古を行っています。 同協会は、例年、各道場間の対抗戦である日本大使杯や、正しい剣道を普及させるための昇段審査、セミナーも開催しています。また、同協会は、日本文化を紹介するイベントにも参加し、剣道の基本動作や技術、道具等を説明するのみならず、日本武道の精神、心構えも教えています。 近年、同協会は、剣道の一種である居合道や杖道の稽古も行っています。
<PICTURES>
1 ヴァイラッパン・マレーシア・サバ大学教授

2 クマラグル・ラマヤ・マレーシア工科大学(UTM)准教授

3 ハスパリナ・マレーシア日本国際工科院(MJIIT)日本語・日本文化センター長

4 ケネス・チュン・マレーシア折り紙協会会長

5 教員養成国際語学キャンパス(IPGKBA)の日本語教員養成プログラム

6 マレーシア剣道協会(MKA)